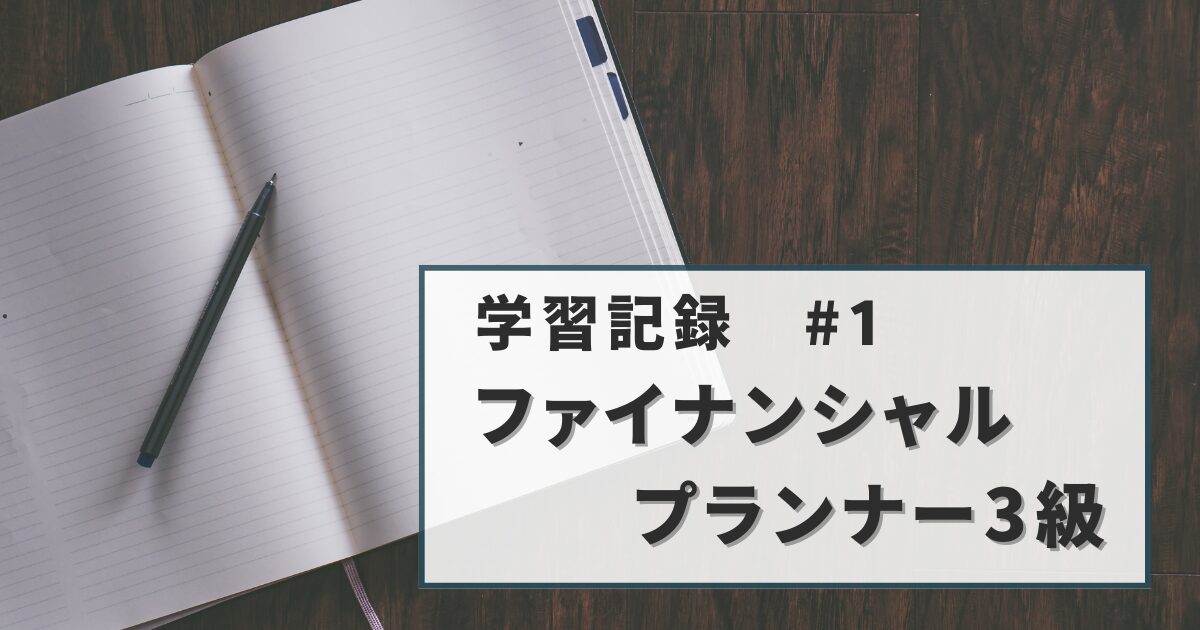さっそく学習を進めていますが、覚える日本語が多く苦労しています。
前半部分は学ばなくても答えられる当たり前のような内容も多かったのですが、後半は言葉の微妙な違いに苦労しました。
今いち頭に入らない内容もあったので、忘備録的に記事を書いてみようと思います。
1.ライフプランニングの手法
人の一生における出来事をライフイベントといい、その中でも
- 教育資金(子どもの教育費用)
- 住宅取得資金(住宅にかかる費用)
- 老後資金(老後にかかる費用)
この3つは資金の額が大きいため、3大必要資金といいます。
このあたりは将来の自分にも関わる内容なので、興味を持って学ぶことができました。
2.資産計画を立てる際の6つの係数
微妙な言葉の違いがあったり、言葉と内容がなんとなく一致しなかったり
この内容がどうしても頭に入らなかったので、難しいことは除いて、自分の言葉で簡単に表にまとめてみました。
| 係数名 | 説明 |
|---|---|
| 終価係数 | 一定額を、何年間か運用したとき、いくらになるか |
| 現価係数 | 何年間か運用した結果、一定額にしたい。最初のお金はいくら必要か |
| 年金終価係数 | 毎年一定額を積立て、運用したときにいくらになるか |
| 年金現価係数 | 毎年一定額を一定期間受け取りたい。最初のお金はいくら必要か |
| 資本回収係数 | 一定金額を一定期間で取り崩すしたい。毎年いくら取り崩せるか |
| 減債基金係数 | 一定金額を一定期間後にほしい。毎年いくら積み立てるか |
「終価」と言葉がつくときは、最終的な価格としていくらになるか
「現価」と言葉がつくときは、現在の価格としていくら必要か
「資本回収」のときは、取り崩すという言葉がキーワードになりそう(取り崩すには最終的になくすという意味が含まれる様子)
「減債基金」は、最終的に必要な金額があり、それに向けていくら積立が必要か
大まかにこのような特徴があるのかなと思います。
基本的にFP3級試験は選択式なので、完璧に覚える必要はなく、キーワードから知識を引っ張ってこられるかが重要です
3.社会保険の種類
- 医療保険
- 介護保険
- 労災保険
- 年金保険
- 雇用保険
よく聞く単語がたくさん出てきました。
将来のことを考えると、これらの保険についてはかなり自分事として学習できました。
保険と言いつつ、満額出るということはなく、だいたい2/3くらいの金額しか補助されないことが多いということを知り、何だかやりきれない思いです。
まとめ
勉強を進めると、知っている言葉が多く出てくるので、かなり能動的に学習ができたと思います。
勉強をすればするほど、将来のことを考えていかなければならないのだなと、何だか切ない気持ちになります。
将来を見据えるという意味でも、この資格の学習をすることは非常に意味がありますね。